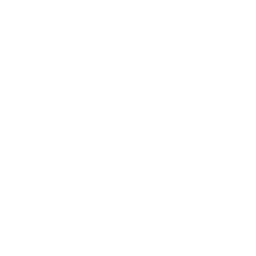
A1:
世界中に放射能汚染が広がった1986年のチョルノービリ原発事故の2年後に、日本国内で干ししいたけから高レベルの放射能が検出されました。グリーンコープは食品の放射能汚染の実態を知り、自主的に判断できるように1989年から供給する食品の放射能測定を始め、共生の時代で結果を報告してきました。
2011年3月11日、東日本大震災にともなう東京電力福島第一原子力発電所の事故により、大量の放射性物質が環境中に放出されたことを受けて、2011年10月、グリーンコープは組合員へ、企画する商品の情報を正しく伝えるために、食品を中心として商品の放射能測定をする放射能測定室を設置しました。現在では、高性能の測定器(ゲルマニウム半導体検出器)2台で放射能測定し、結果を公表しています。
A2:
放射性物質から出される放射線による被ばくには、大気中や地表の放射線を身体の外から浴びる外部被ばくと、呼吸や汚染された食品を摂取することで身体の中に摂り込んだ放射性物質が放出する放射線による内部被ばくの2つがあります。放射性物質は一旦体内に入るとなかなか排泄されず、放射線を出し続けます。安全な被ばく量はここまでという閾値(しきいち)はありません。
放射線は目に見えず、においもないため、人間が五感で感じることはできません。グリーンコープでは、カタログで取り扱う食品などについて、その中に残留する放射性物質(ヨウ素-131、セシウム-134、セシウム-137)の検査を実施し公表することで、組合員が選べるようにしています。
A3:
放射線は目に見えず臭いもなく、無害にする方法もまだ見つかっていません。放射性物質が出す放射線はモノを通り抜ける力を持っています。それがヒトの身体を通り抜けるときに細胞の遺伝子を傷つけてしまいます。一旦傷ついた遺伝子は長い年月をかけてじわじわと身体に影響を与えます。細胞分裂の回数が多い子どもが受ける放射能の影響は大きく、成長期に遺伝子が影響を受けてしまうと、がんなどの病気になる確率が高くなると言われています。
A4:
核実験や原子力発電所の事故などで、環境に放出される放射性物質の割合が高いのが、ヨウ素とセシウムです。グリーンコープでは、ヨウ素-131とセシウム‐134、セシウム‐137について測定しています。ヨウ素-131の物理学的半減期(放射線の量が半分になるまでの時間)は8日、セシウム‐134は2年、セシウム‐137は30年と長くなっています。それらの放射性物質は、飛び散ったり、土壌にそのまま残ったり、成層圏まで舞い上がったものが雨などで少しずつ地上を汚染し、農・畜・水産物などに取り込まれている可能性があり、検査をすることで汚染の実態を明らかにできます。セシウムやヨウ素から放出される放射線はガンマ線とベータ線です。ゲルマニウム半導体検出器で測定できるガンマ線の測定を行っています。なお、セシウムを測定することで他の核種の排出量も推計することができます。グリーンコープでは放射能測定室開設時の方針に基づいて検査結果のすべてを公開しています。
A5:
1986年のチョルノービリ原発事故直後、食品中に残留する放射能の日本での暫定基準値は、チョルノービリと陸続きであるヨーロッパと同じ「放射性セシウム370ベクレル/kg」でした。グリーンコープは、「買い、食べる側にとっての目安になる自主基準値が必要である」として検討を重ね、自主基準値を「放射性セシウム10ベクレル/kg」以下としました。
2011年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所の重大事故によって、アクションレベル「10ベクレル/kg」を守り通すことは困難とも考えられましたが、生命を守るために最善の努力をしたいと考え、「10ベクレル/kg」を継続することにしました。現在も、10ベクレル以上の数値が検出された場合は理事会で検討し、取り扱いを決定することにしています。
| グリーンコープ独自基準 | 国の基準 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 基準値 | 区分 | 基準値 |
| すべての食品 | 10 | 飲料水 | 10 |
| 牛乳 | 50 | ||
| 一般食品 | 100 | ||
| 乳児用食品 | 50 | ||
(単位:ベクレル/kg)
※国の基準を超えた場合は、直ちに出荷停止です。
A6:
放射線を出す物質を「放射性物質」、放射性物質が放射線を出す能力のことを「放射能」と言います。放射性物質を電球に例えると、放射線は光、放射能は電球が光を出す能力に例えられます。
放射性物質はエネルギー的に不安定であるため、エネルギーを放出して安定した物質になろうとします。その変化を壊変といい、その時に出すエネルギーが放射線です。放射線には、物質を突き抜ける力の強さや、物質と反応する能力の強さによって、アルファ線、ベータ線、ガンマ線、など、いくつかの種類があります。セシウムやヨウ素はベータ線とガンマ線を出します。
A7:
放射性物質が放射線を出す能力の大きさを表す単位が「ベクレル」、人体が受ける放射線被ばく線量を表す単位が「シーベルト」。
ストーブに例えると、ストーブから放出される熱の総量を表す単位がベクレル、そこから人が実際に受ける熱量を表すのがシーベルトです。
ベクレルは、主に食品や水・土壌の中に含まれる放射性物質が放射線を出す力の強さを表す場合に「1kgあたり500ベクレル(500Bq/kg)」のような形で使います。
シーベルトは、外部被ばくや内部被ばくによって実際に人体が影響を受ける放射線量を表す場合に「1時間あたり1ミリシーベルト(1mSv/h)」のような形で用います。
A8:
食品中に残留する放射能の測定では、測定器の性能や測定する物によって、それぞれの測定時間や測定量によって、ある値以上測れないという最小の値があります。それが「検出限界値」です。自然界には宇宙や大地などに由来する放射線も存在することから、厚生労働省は、検査結果には検出限界値を表示するように、2011年9月に通達しました。なおグリーンコープの場合は、精度の高いゲルマニウム半導体測定器を使って測定していることから、検出限界値が1ベクレル前後で測定できています。
放射能検査結果一覧表の「結果」の欄の「検出せず」は、右の欄の数値(検出限界値)以下であることを示しています。