最初にマスコバド糖工場(ATMC:Altar Trade Manufacturing Corporation)のアシスタントマネージャー(副工場長)のスティーブさんから工場の概要説明を受けた。彼は品質管理部長も兼任していて「グリーンコープからのクレームを受ける係りをしている」と笑顔であいさつした。労働者68名。うち正規職員(フルタイムのスタッフ)は20名。事前のスケジュールでは工場内は整備中で中には入れないとのことだったが私たちはついている。 これまでの工場の見学に加え、9月に稼働を始める新工場の試運転の日と重なり、新旧2つの工場見学が出来た。
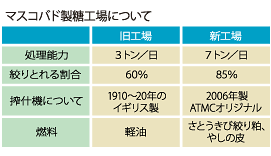
今日の試運転から1ヶ月間の製品は国内で流通させる予定とのこと。2つの工場あわせて1日に10トンのさとうきびを処理できるようになる。工場では運ばれてきたさとうきびを機械にかけ搾り、搾り取られたさとうきびジュースをメッシュで濾し、窯で煮詰めて、広い大きな流し箱のようなものに入れられスコップでかき混ぜていくと段々サラサラになって私たちが口にする製品になっていく。最後の過程で取り残されたようにあるブロック状のものがビン入りで売られていておみやげに購入した。
途中でさとうきびジュースを濾す、濾しアミを見せてもらった。以前は針金状のアミを使用していたが、その一部が製品に混入してクレームが上がり、現在のものに変更したとのことだった。また、袋詰した製品はダンボールに入って運ばれるが、ダンボールの箱底を止める大型のホッチキスの針が製品に混入していたことがあったということで現在、箱は透明のテープで止められていた。「グリーンコープの皆さんからのクレームを参考に今回の新工場は設計している。クレームのおかげなのです」と私たち組合員のクレームがこのフィリピンのネグロスまできちんと届き、それがしっかり生かされていることを実感できたのと同時にとても嬉しかった。日本からのクレームのファックスの綴りを見せてもらった
できあがったマスコバド糖の袋詰め作業は全て手作業だ。私たちの手に届くまでに実に多くの人たちの手が関わっているのだと実感した。 新旧の工場どちらも入るときは、帽子、マスク、エプロンを着け、白長靴に履き替え、消毒液で手を洗い、ローラーで服のほこりを取るなど、衛生面には徹底した配慮がしてあった。
ネグロス島では5月からさとうきびの収穫が本格的に始まる11月までは「死の季節」といわれる。これはさとうきびが1年に1度収穫できる作物でさとうきびを植え付けたあとはその生育を待つだけとなって、さとうきび労働者は仕事が無くなり収入が途絶えるから。「死の季節」という言葉はネグロスでは良く出てくる。
一方で工場の稼動中の9月から4月までは24時間のフル操業。年間240トンのマスコバド糖製品は国内での消費の他に日本へ40トン、大きな市場はEU連合でチョコレートにも使用される。新工場を作るほど日本で売れているのかと思った私は「作られたマスコバド糖はどこへ行くのですか?」質問をしてその謎が解けた。私たちが口にするマスコバド糖はいまや、有機認証のついた一級品なのだ。「飢餓の島の救済」という文字が当初の製品には印刷されていた。ヨーロッパ向けの製品は箱入りでそれを見た私たちは「グリーンコープももっとおしゃれなのがイイ」などと思った。 |